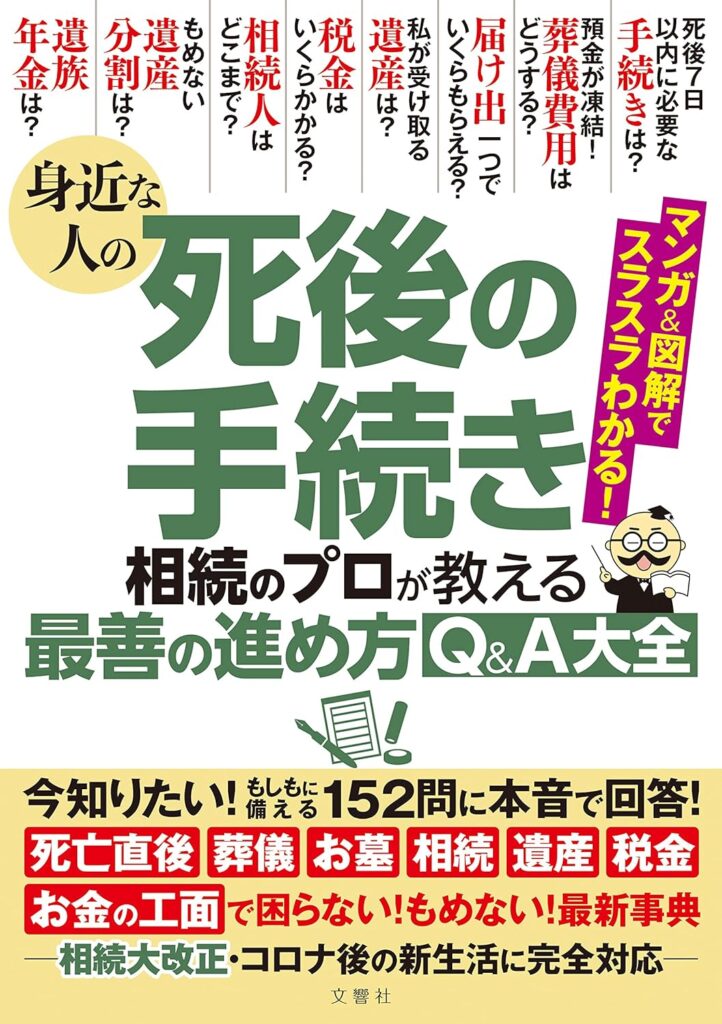はじめに
60代になると相続は他人事ではなく自分の課題になります。
残された家族の生活を守るには、財産を円滑に渡す準備と相続税の負担を減らす工夫が欠かせません。相続税は基礎控除があるとはいえ、不動産や預貯金が一定額を超えると課税対象となり、想像以上の金額になることがあります。
まず、国税庁の相続税試算コーナーで家族構成と財産額を入力し概算額を把握しましょう。操作は3項目を入力するだけで簡単ですが、不動産評価は大まかなため結果をそのまま信じず、あくまで目安と考えることが重要です。試算結果が0円でも配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用した場合は申告義務が残るなど、相続税には見落としやすいルールが多くあります。また生命保険や賃貸不動産を使った節税策には保険料の高額化、空室リスクといった落とし穴があります。大切なのは早めに家族で話し合い、相続専門の税理士に相談して自分に合った計画を立てることです。
本記事では試算の具体的な手順、代表的な対策、よくある間違いを初心者にも分かりやすく解説します。
<関連記事>
相続税の基礎知識
相続税の仕組みと課税対象
相続税は、亡くなった人の財産を相続人が受け継ぐときに課される国税です。現金、預貯金、土地建物、株式など国内外の財産が対象になります。本人が保険料を払っていた死亡保険金や死亡退職金も、みなし相続財産として課税対象になります。一方で、墓地墓石仏壇など礼拝用の財産は非課税です。生命保険金と死亡退職金には、法定相続人×500万円の非課税枠がありますが、契約形態を誤ると適用外になるため要確認です。
基礎控除と課税遺産総額の計算式
相続税額を考える最初のステップは基礎控除の確認です。式は、
3000万円+600万円x法定相続人の数
です。遺産総額がこの金額以内なら相続税は発生しません。
2015年の改正で、旧式の5000万円+1000万円×人数から縮小され課税対象が増えています。法定相続人は相続放棄をしても、人数に含める点や養子は実子がいる場合、1人までしか数えられない点に注意しましょう。課税遺産総額は、遺産総額に相続開始前7年以内の贈与などを加算し、債務・葬式費用・非課税財産を差し引いた課税価格から基礎控除を引いて求めます。
税率・速算表の読み方と配偶者控除
課税遺産総額を法定相続分で仮に分け、各人の取得金額に速算表の税率を掛けると相続税の総額が出ます。
例えば、取得金額1000万円以下は税率10%、控除額0円、1500万円超3000万円以下は税率15%、控除額50万円というように段階的に税率が上がる超過累進課税です。総額を実際の取得割合で按分し、配偶者控除などを差し引くと各人の納税額が確定します。
配偶者が取得する財産が1億6000万円以下、または法定相続分以下なら、配偶者控除で税額は0円になりますが、申告書の提出は必須なので忘れないようにしましょう。
国税庁「相続税の試算コーナー」でシミュレーション
事前にそろえる資料(資産一覧・債務・相続人情報)
試算コーナーを開く前に、被相続人の資産一覧、債務一覧、相続人の人数をまとめましょう。
- 資産は、預貯金、証券、土地・建物、保険金、死亡退職金などの概算額で十分です。
- 不動産は、固定資産税、評価証明書に記載された評価額を目安にします。
- 債務は、住宅ローン、未払金、葬儀費用の見込みを合計します。
- 相続人は、配偶者子どもの人数、養子の有無を正確に数えます。
シミュレーションの入力ステップ
国税庁の相続税計算シミュレーションの入力ステップについて説明します。

試算は、
- 配偶者の有無
- 法定相続人の数
- 各財産の金額
の三つを入力すれば結果が表示されます。画面の案内に従い、現金預貯金その他資産の欄へ金額を入力し、土地建物は自用地貸付地など種類ごとに分けて入力します。最後に借入金葬式費用をマイナス項目として入れ、試算ボタンを押すだけです。操作は10分もあれば完了します。
ケーススタディ:遺産総額8,000万円・配偶者+子2人の場合
例として以下のケースを試算します。
- 遺産総額8000万円(内訳:自宅土地建物4000万円、預貯金2500万円、上場株式1500万円)
- 相続人は配偶者と子2人

入力結果画面では、

課税価格から基礎控除4800万円を差し引いた課税遺産総額3200万円が示されます。

速算表による税率適用で相続税総額は約350万円と表示されます。配偶者の税額軽減を適用すると、

納税額は0円になる結果が出ます。
出力結果の見方と注意点(納税額・二次相続への影響)
表示される税額は概算です。
不動産の正確な評価や名義預金の有無によって、実際の税額は大きく変動します。また、配偶者控除や小規模宅地等の特例適用後に、納税額が0円でも申告書提出義務がある点を見落とすと、後で追徴課税の恐れがあります。相続開始前7年以内の贈与や、生命保険の非課税枠も自動では反映されないため、必要に応じて再計算が必要です。試算コーナーは、納税額が発生しそうかどうかを早期に把握する入口ツールと考え、専門家による詳細確認へ進むのが安心です。
試算結果を印刷し、資産一覧と合わせて税理士へ持参すると相談がスムーズに進みます。まずは一度試してみて、対策の優先順位を決めましょう。
シミュレーション結果から見える課題
試算コーナーで数字を可視化すると納税資金、二次相続、生活設計という三つの課題が浮かび上がります。これらは時間を味方につければ解決策を選べますが後回しにすると選択肢が急速に狭まります。家族と情報を共有し専門家と連携して早めに行動することが安心相続への第一歩です。
納税資金をどう確保するか(不動産中心の遺産の落とし穴)
シミュレーションで税額が表示されると、まず気になるのは納税資金です。
相続税は、原則現金一括払いで期限は相続開始から10か月です。不動産中心の遺産の場合、現金が足りず自宅を売るしかないという声が少なくありません。不動産は評価額より高く売れれば良いのですが、空室リスク修繕費用、買い手探しの時間などハードルが多く、現実は思うように資金化できません。生命保険で納税資金を準備する方法もありますが、60代で新規加入すると保険料が高額になり元本割れの危険もあります。
保険料総額と非課税枠効果を冷静に比較し、無理のない範囲で現金準備策を検討することが欠かせません。
二次相続リスクと分割トラブルの可能性
配偶者が多くの財産を受け取ると、一次相続では配偶者控除で税額ゼロでも、その後に配偶者が亡くなる二次相続で課税額が急増する恐れがあります。特に子が複数いる家庭では、「誰が不動産を持つか」「現金をどう分けるか」で対立が起きやすく、二次相続の方が争いが深刻になりがちです。一次相続の段階で、遺産を配偶者と子にバランス良く配分したり生前贈与を組み合わせて相続財産自体を圧縮したりするなど、将来を見据えた配分計画が必要です。遺言書で具体的な分け方を示し、家族会議で意思を共有することがトラブル防止の近道です。
相続人の生活設計への影響
税金や分割方法が未定のまま相続を迎えると、相続人は納税資金の捻出や不動産管理で生活設計が狂うことがあります。例えば、賃貸アパートを相続した子が、空室対策や修繕費に追われ本業に支障を来すケースや、ローン付き物件を引き継いで返済が家計を圧迫するケースが典型例です。さらに、介護費用や教育費など各家庭のライフイベントが重なると負担は一層大きくなります。
シミュレーション結果を踏まえ早めに資産を棚卸しし、「納税資金は誰がどう負担するか」「不動産を保有か売却か」などを具体的に決めることが大切です。専門の税理士やファイナンシャルプランナーに相談し家計シミュレーションも併用すると家族全員が安心して暮らせる計画を立てやすくなります。
税理士の相談はこちらをぜひご活用ください。[PR]
効果的な相続税対策
生前贈与、生命保険、不動産活用、家族信託、遺言書は相続税対策の柱ですがどれもメリットとコストが表裏一体です。「早く小さく試す」「数字で比較する」「専門家と二重チェックする」の三点を意識すれば失敗を防げます。シミュレーションで見えた税額を出発点に自分に合った組み合わせを考え、家族と共有し、相続専門の税理士へ早期相談することが安心相続への近道です。
生前贈与(暦年贈与/相続時精算課税)の活用ポイント
毎年110万円以内を子や孫へ渡す暦年贈与は、最も手軽な節税策です。ただし2024年以降は、相続開始前7年以内の贈与が課税価格に戻される期間が段階的に延びます。早めに始めれば、戻し入れの影響を小さくできます。2,500万円まで非課税になる相続時精算課税は、不動産や株式など値上がりしそうな資産を早く移す時に有効です。「教育資金1,500万円」「結婚子育て資金1,000万円の一括贈与」特例も活用できますが、残額が相続財産に戻る点に注意しましょう。贈与契約書の作成と、銀行振込で「贈与の証拠」を残すことが脱税認定を防ぎます。
生命保険で納税資金を準備する方法
死亡保険金は、「500万円×法定相続人」の非課税枠があるため、現金で残すより相続税を抑えやすく納税資金も一度に受け取れます。ただし、60代で新規加入すると保険料が高く、早期解約で元本割れしやすい点が弱点です。加入前に保険料総額と非課税メリットを試算し、健康状態による保険料割増も確認しましょう。契約形態は、保険料負担者と被保険者が被相続人、受取人が相続人でなければ非課税が使えません。
家族信託・任意後見制度で資産管理をスムーズに
現金を賃貸不動産に組み替えると相続税評価額が下がりやすく、小規模宅地等の特例で最大80%減額が可能です。しかし、空室や修繕費が増えると赤字になり、ローン返済が重荷になります。借入期間は建物の耐用年数内に収め、減価償却切れで税負担が増える時期と返済終了時期をそろえると安全です。不動産は分割が難しいため、誰が相続しどう管理するかを事前に話し合うことが不可欠です。
不動産の評価減と小規模宅地等の特例
認知症対策として、家族信託で信頼できる子に資産管理を任せておくと、売却や運用が止まらず納税資金の手当ても容易になります。任意後見契約を公正証書で結んでおくと、判断能力が低下しても家族が代理で手続きできます。節税効果は直接ありませんが、資産が凍結されるリスクを減らし、結果的に円滑な納税や分割に役立ちます。
遺言書作成と分割シナリオの事前合意
公正証書遺言なら、形式不備の心配が少なく家族が迷わず遺産を受け取れます。配偶者と子の取り分を一次二次相続まで見据えて書くと、将来の税額とトラブルを同時に抑えられます。作成後も家族構成や資産状況が変われば必ず見直しましょう。
税理士の相談はこちらをぜひご活用ください。[PR]
相続税の考え方でよくある間違い
相続税には、聞きかじりの知識が独り歩きしやすい落とし穴があります。以下の誤解は、「手間を省きたい」という思いから生まれやすい事例です。まずは、国税庁シミュレーションで概算を把握し、上記ポイントを照らし合わせてみてください。そのうえで、相続税に詳しい税理士に早めに相談すれば、申告漏れや無駄な納税を防ぎ、家族の安心につながります。
誤解1 基礎控除内なら誰でも非課税
基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人で計算しますが、相続放棄した人も人数に数えてしまい控除額を過大に見積もってしまう点に注意が必要です。さらに、名義預金やタンス預金を申告し忘れると、追徴課税の対象になります。
誤解2 配偶者控除があるから心配ない
配偶者が取得した財産が1億6000万円以下または法定相続分なら、税額は0円になりますが申告書の提出は必須です。また、配偶者が亡くなる際の二次相続では、控除が使えず税負担が跳ね上がるため、一次相続からバランス良く分ける視点が欠かせません。
誤解3 毎年110万円ずつ贈与すれば安心
暦年贈与は手軽な方法ですが、2024年からは相続税の計算に加えられる贈与の期間が、これまでの3年から7年に延長されます。加えて、贈与契約書や銀行振込の記録を残していないと「毎年まとめて渡した定期贈与」や「名義だけ預けた預金」とみなされ、結果的に相続税がかかる恐れがあります。
誤解4 不動産は評価が低いから安全
土地建物は現金より評価額が下がりやすいものの、空室リスク修繕費ローン返済が重荷になると相続人の家計を圧迫します。借入期間が耐用年数を超えると、減価償却が切れ税負担が増える点も見落とされがちです。
誤解5 生命保険は万能の節税策
死亡保険金は、500万円×法定相続人の非課税枠がありますが、60代以降の加入は保険料が高騰し、元本割れの危険があります。保険料負担者と被保険者が被相続人かどうか、契約形態を誤ると非課税枠が使えないため、慎重な確認が必要です。
なお、相続に関する情報を本で調べることもお勧めします。[PR]
身近な人の死後の手続き 相続のプロが教える最善の進め方Q&A大全
大好評!14万部突破!
Amazon売れ筋ランキング(2024/9/9時点)
・カテゴリ「民事裁判関連」1位
・カテゴリ「民法・民事法」1位
対策を進める際の実務的課題
相続対策は、節税テクニックよりも「情報共有」「専門家連携」「資金計画」が実務の成否を左右します。
- 家族会議で現状を見える化
- 信頼できる税理士に早めに相談
- 老後生活費と節税のバランスを調整
この3ステップを意識すれば慌てずに円満相続へ近づけます。
家族間コミュニケーションと情報共有の壁
相続はお金の話が中心になるため、「言い出しにくい」「揉めそうで怖い」という心理的ハードルがあります。まずは自宅の食卓で構いません。「国税庁の試算をやってみたら税金が出るかもしれない。みんなで考えよう」と、事実を共有すると感情論になりにくくなります。話し合いは一度で終わらせず、年1回の家族会議を目安に継続しましょう。
専門家(税理士・司法書士・ファイナンシャルプランナー)の選び方と費用感
相続税は評価と申告の難易度が高く税理士のサポートが欠かせません。
選ぶポイントは、
- 相続申告の実績件数
- 初回相談で試算書を提示してくれるか
- 料金体系が明確か
の3点です。報酬相場は、遺産総額の0.5~1%。例として遺産1億円なら50~100万円が目安です。初回無料相談を使い2~3事務所を比較すると安心です。司法書士は登記、ファイナンシャルプランナーは資金計画と役割が違うため、必要に応じてチームで依頼します。
資産・負債棚卸しチェックリスト
対策の前提は正確な資産把握です。
- 預貯金…通帳コピーと残高証明書
- 証券…取引報告書、株式数、評価額
- 不動産…登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 保険…契約内容一覧、解約返戻金額
- 借入金…ローン残高証明、保証人情報
- その他…タンス預金、貸付金、ゴルフ会員権など
A4の資料1枚に一覧化し、クラウド保存すると家族で共有しやすく紛失防止にもなります。
生前対策と老後資金のバランス
「贈与や不動産購入で節税したが老後資金が足りなくなった」という本末転倒は避けたいところです。目安は、夫婦2人の生活費×余命年数+医療介護費を安全資金として確保し、残りを対策に回すイメージです。足りない場合は、
- 贈与額を抑える
- 生命保険を短期払にする
- 不動産投資を見送る
など柔軟に調整します。ファイナンシャルプランナーにキャッシュフロー表を作ってもらうと数字で判断でき安心感が増します。
スケジュール管理と書類整理
相続発生後は10か月で申告というタイトな期限があり、慌てるとミスが起こりやすくなります。生前に「資産一覧・保険証券・パスワード一覧」を一つのファイルにまとめ、「遺言書の保管場所」「税理士連絡先」を付箋で明示しておくと家族が迷いません。大切な書類は、公証役場や法務局の自筆証書遺言保管制度を活用すると紛失リスクを減らせます。
まとめ
相続税対策の出発点は、国税庁試算コーナーで自分の税額を数値化することです。概算とはいえ、課税の有無が分かれば家族会議を始めやすくなります。次に、基礎控除や配偶者控除超過累進課税の仕組みを正しく理解し、誤解を避けましょう。
試算から浮かぶ課題は、
- 納税資金の確保
- 二次相続リスク
- 相続人の生活設計
の3つです。生前贈与、生命保険、不動産活用、家族信託、遺言書を組み合わせれば負担は軽減できますが、60代からの新規保険加入や賃貸不動産投資には高コストや空室リスクが伴います。
まず、夫婦の生活費と医療介護費を安全資金として確保し、残りを節税策に回す発想が重要です。資産一覧、債務一覧、パスワード一覧を一つのファイルにまとめ、年1回の家族会議で更新しながら税理士相談を早めに予約しましょう。申告期限まで10ヶ月しかない相続発生後に慌てないためには、生前から情報と役割を整理することが決め手です。数字を見える化し家族と専門家で協力すれば、節税と円満承継の両方が実現できます。