はじめに
電気料金は固定費と従量課金に加え、燃料費等調整と再エネ賦課金、そして一時的な政府支援の有無で毎月変わります。本記事では仕組みを基礎から整理し、政府支援がない前提でも家計を守れるように具体策へ落とし込みます。全国向けの内容で、数値例は東京電力の従量電灯Bを参照します。
政府の電気料金支援はなぜ月ごとに単価が違うのか
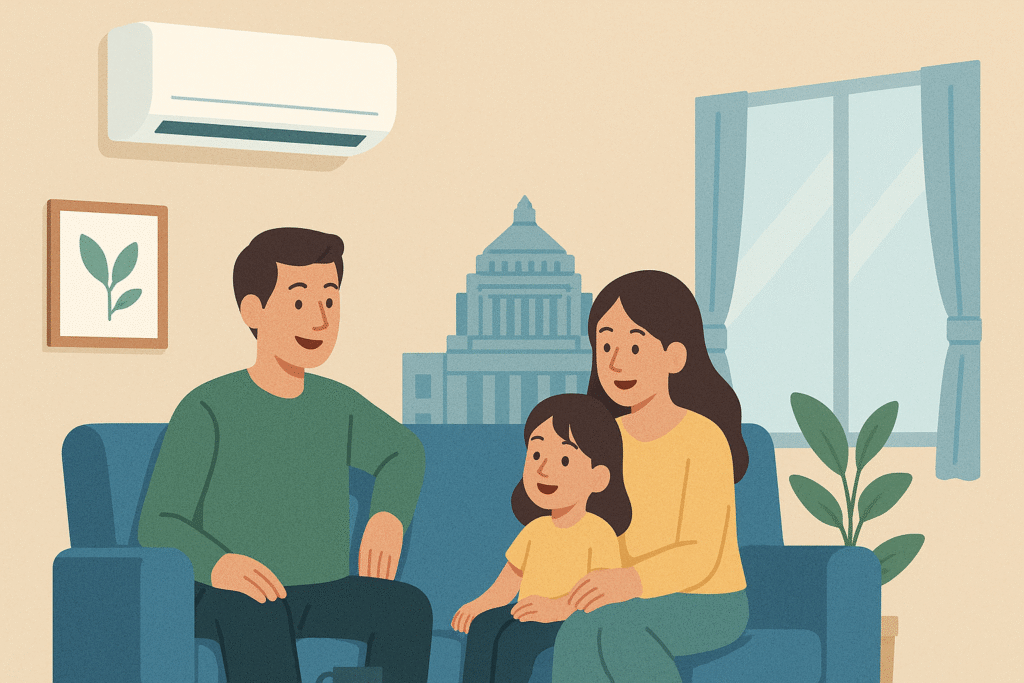
まず枠組みを押さえます。2025年夏の電気ガス料金負担軽減支援は、家庭の低圧契約に対し、当月の使用量に「月ごとに定められた単価」を掛けた額を自動で差し引く仕組みです。ここで読者が迷いやすいのが「なぜ7月と8月で単価が違うのか」という点。政策設計上の理由を、先に骨子で確認しておきます。
単価が月ごとに違う理由
1 冷房需要のピーク対策として、最も負担が大きくなる8月を手厚く設計している
2 期間限定の重点配分で、月別にメリハリを付けて負担緩和効果を最大化するため
3 支援単価は政策で決める定額であり、市況に毎月自動連動する制度ではない
4 低圧と高圧で水準が異なるため、家庭向けは低圧の値を確認する
実務としては、対象月かどうかと、自宅の当月使用量が何kWhかの二点を確認すれば、値引き額は「使用量×当月単価」で直ちに算出できます。なお、日数が長い月でも、単価はあくまでkWh当たりの定額なので、最終的な値引き額は使用量の多寡で決まります。
注意点
・対象期間と単価は公表内容に従うため、最新の発表で確認する
・値引きの表示場所は各社の明細レイアウトに依存する(別項の「明細は公式ページで正しく確認する」を参照)
なぜ電気料金は毎月上下するのか?
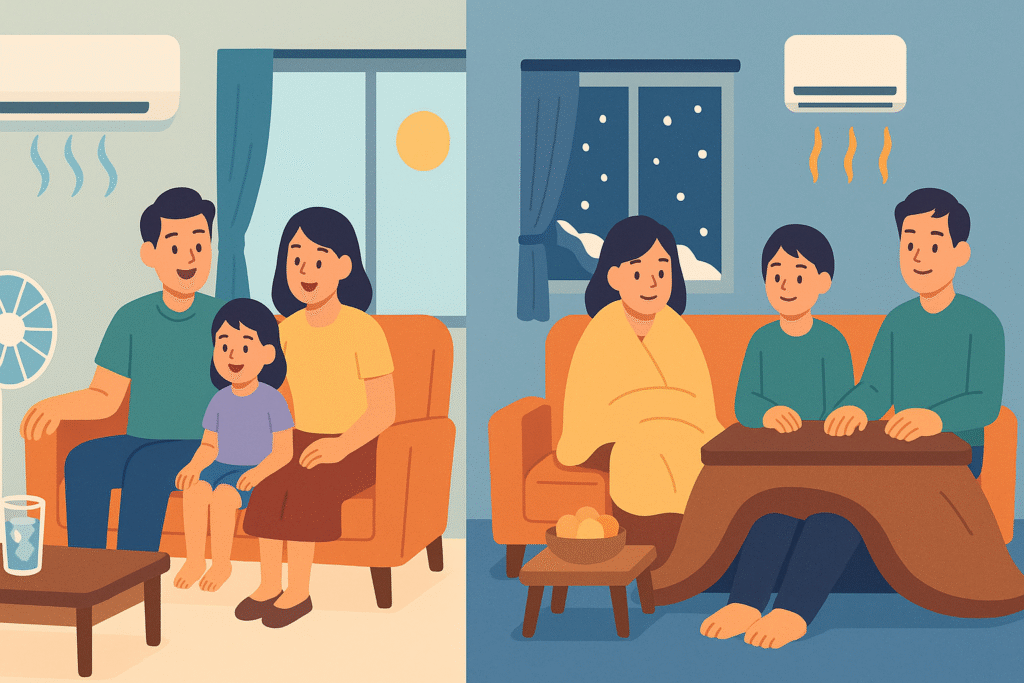
「先月より高いのはなぜ?」に答えるには、料金の仕組みを“動く部分”と“動かない部分”に分けて見るのが近道です。下の一覧は、毎月の増減に効く代表的な要因です。まずチェックの順番だけを頭に入れて、次の章で自宅の明細に当てはめてみましょう。
毎月の上下を生む主な要因
- 使用量の変動 気温 在宅時間 家電稼働時間でkWhが変わる
- 段階料金の境目をまたぐか 120kWhや300kWhを超えると高い単価帯に乗る
- 燃料費等調整の毎月変動 原油 LNG 石炭の日本着価格と為替の数か月平均と基準価格の差を単価化して毎月反映
- 再エネ賦課金の切替タイミング 年度単価は固定だが適用期間の切替月は見え方が変わる
- 政府支援の有無と月別単価 対象月だけ値引きが入るため非対象月との単純比較は不可
- 料金改定やプラン変更 契約容量や料金表の改定で水準が変化
- 検針周期と請求日数の差 検針日の前後で当月日数が変わりkWhと金額が増減
実務上の確認手順はシンプルです。今月と先月のkWh差を見て、段階帯の滞在時間を確認し、当月の燃料費等調整単価と合計額、支援の適用有無、年度切替時の再エネ賦課金単価を順にチェックすれば、増減の理由は必ず分解できます。
電気料金の基本構造を理解する
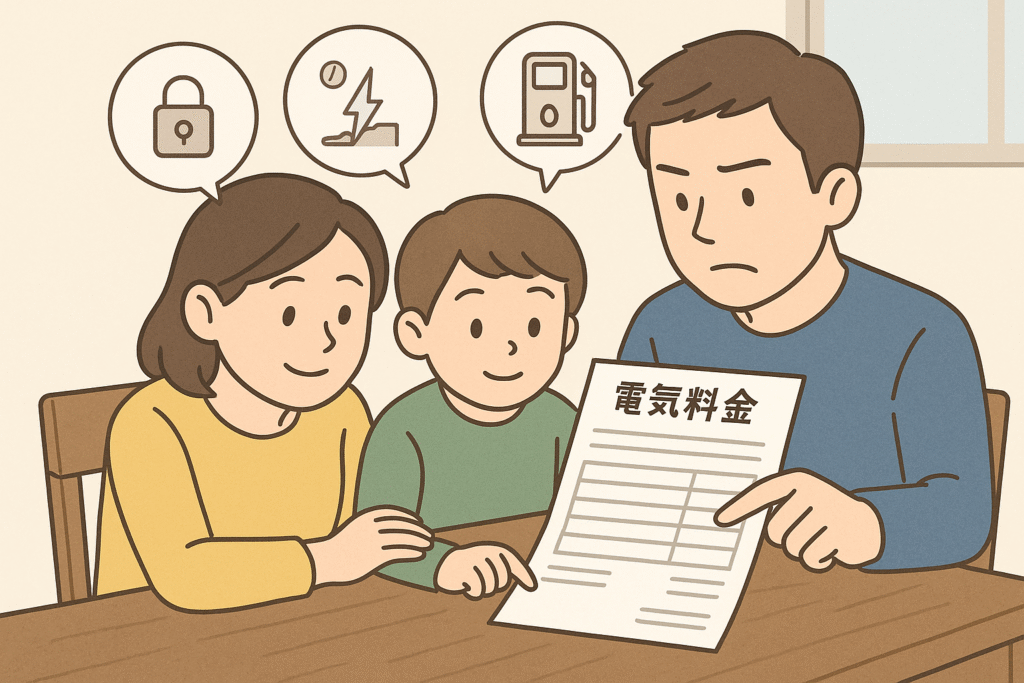
ここで全体像をいったん整理します。電気料金は、固定の基本料金、使った量に応じた電力量料金、毎月変わる燃料費等調整額、年度で固定される再エネ賦課金の四つを合算し、該当月であれば政府支援の値引きを最後に差し引いて確定します。自宅の費目ごとの動き方を知っておくと、翌月の見通しも立てやすくなります。
参考として、東京電力の基本料金と電力量料金の単価は次のとおりです。
| 区分 | 単価 |
|---|---|
| 基本料金:10Aあたり | 311.75円 |
| 電力量単価:第1段階 〜120kWh | 29.80円kWh |
| 電力量単価:第2段階 121〜300kWh | 36.40円kWh |
| 電力量単価:第3段階 301kWh〜 | 40.49円kWh |
具体例で見る計算フロー
2025年8月に東京電力の従量電灯Bプラン30Aで400kWhを利用した時の計算を見てみましょう。実際の計算は「式→手順→確認先」の順で追うと迷いません。まず、最終請求額は次の式で概観できます。
最終請求額 = 基本料金 + 電力量料金三段階の合計 + 再エネ賦課金単価×使用量 + 燃料費等調整単価×使用量 − 政府支援単価×使用量
この式に沿って、数字を当てはめていきます。
- 基本料金を入れる
30Aなら935.25円
[確認方法]東京電力の料金メニュー、基本料金欄 - 電力量料金を三段階で合計する
0〜120kWh×29.80円 + 121〜300kWh×36.40円 + 301〜400kWh×40.49円 = 3576円+6552円+4049円=14177円
[確認方法]東京電力の料金メニュー、電力量料金の段階別単価 - 再エネ賦課金を加える
3.98円×400kWh=約1592円
[確認方法]経済産業省や電力会社の再エネ賦課金、単価告知 - 燃料費等調整額を反映する
当月の燃料費等調整単価×400kWh(毎月更新でプラスにもマイナスにも振れる)
[確認方法]東京電力の燃料費等調整、単価告知または明細の単価欄 - 該当月なら政府支援を差し引く
2025年8月は2.4円×400kWh=960円を控除
[確認方法]政府の月別単価告知、明細の値引き欄
ここまでの流れを自宅の使用量に置き換えれば、請求の仕組みを“自分の明細の言葉”に翻訳できます。慣れてきたら、月の途中でも累計kWhと段階帯の位置を見て、月末の着地(300kWhをまたぐかなど)を前倒しでコントロールしましょう。
<関連記事>
[世帯別]補助がなくなるとどうなるか
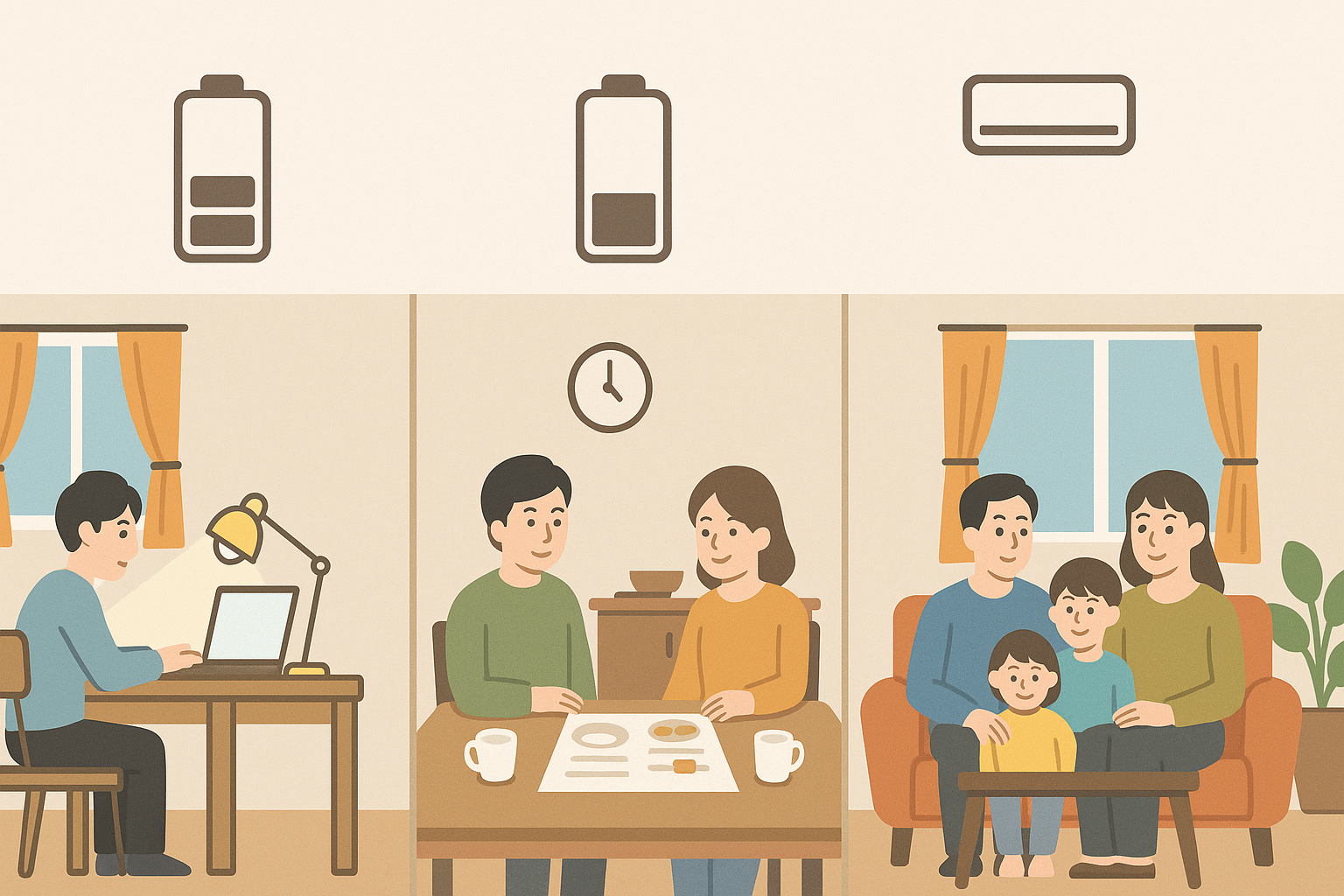
支援がない月の影響は、「当月の使用量×その月の支援単価」に等しい—この考え方だけで素早く見積もれます。ただし、使用量は世帯人数・住まい・季節で大きく変わります。単身の集合住宅でも真夏は200kWh前後に達する例が珍しくなく、二人暮らしなら250〜350kWh、三〜四人の戸建てでは冷暖房期に400kWh前後まで伸びることがよくあります。まずは自宅の月kWhを把握し、下の早見表に当てはめて、補助の有無でどれだけ差が出るかを確かめてください。
| 月使用量 | 7・9月の増分目安 | 8月の増分目安 |
|---|---|---|
| 200kWh | 約400円 | 約480円 |
| 300kWh | 約600円 | 約720円 |
| 400kWh | 約800円 | 約960円 |
| 500kWh | 約1000円 | 約1200円 |
表でおおよその差額感をつかんだら、月末に向けて「300kWhの境目をまたぎそうか」「エアコンや乾燥機の運用で削れる余地はあるか」「常時通電の見直しでベースの消費を落とせるか」をチェックリストとして回すのがおすすめです。
明細は公式ページで正しく確認する
各社で明細の見せ方は更新されるため、単価や項目名は必ず最新の公式ページで確認しましょう。東京電力なら、従量電灯Bの料金メニューで基本料金と段階別単価を、月々の燃料費等調整単価は告知ページや明細の単価欄を、Web検針票の見方はサポートページを、それぞれ参照できます。政府の特設サイトでは、支援の対象期間と月別単価が公開されています。自宅の明細を開き、基本料金→電力量料金→燃料費等調整→再エネ賦課金→政府支援の順に確認すれば、増減の理由は必ず説明できるようになります。
ここからの電気代節約と優先順位

ゴールは明確に、手順はシンプルに。多くの家庭では、まず月300kWhの境目をまたがない運用を狙うだけで、単価の悪化を避けやすくなります。やることは次の五つ。最初の二つ(境目管理と常時通電の棚卸し)から着手すると、早い段階で手応えが出ます。
- 月300kWhの境目を意識 今月あと何kWh使えるかを週1で共有 境目をまたぐ時間を短くする
- 常時通電の棚卸し Wi-Fiルーター 録画機 NAS ゲーム機の待機などを見える化 スリープと省エネ設定を徹底
- 空調は立ち上がり短縮と巡航安定 立ち上がりは風量自動 室温安定後は弱め連続運転 サーキュレーター併用
- 給湯と乾燥はまとめ使い 追い焚き短縮と入浴集中 乾燥の連投と容量オーバーを避け合計ランタイムを削減
- kWh基準でトラッキング 請求額ではなく 使用量 燃料費等調整単価 再エネ賦課金単価 支援の有無を毎月メモ
この“5点セット”を回し続ければ、補助の有無にかかわらず、請求のブレを小さくしながら支出をコントロールできます。
まとめ
補助がなくなると 使用量×月別単価相当の差がそのまま表れます。とはいえ 段階の境目管理 常時通電の削減 空調と給湯の運用見直し kWh基準の管理で 請求の跳ね上がりは抑えられます。まずは自宅の月kWhを確かめ 表2の目安に当てはめて具体的な削減計画に落としてください。
参考文献(一次情報)
- 政府 電気・ガス料金負担軽減支援 特設サイト
- 資源エネルギー庁 燃料費等調整制度の仕組み
- 資源エネルギー庁 エネルギー価格・家計支援の総合ページ
- 東京電力 従量電灯B 料金・単価(旧メニューの参照ページ)
- 東京電力 スタンダードS(関東)料金・単価
- 経済産業省 再エネ賦課金 2025年度単価の公表
- くらしTEPCOweb Web明細の確認ガイド
[無料]家計に役立つ電力診断のご案内
Silver Growth Studioの無料電力診断は、住まいと使い方の条件から、どこを何kWh抑えられるかを可視化することができます。300kWh以内やピーク抑制を現実的に狙い、家計に役立ててください。



